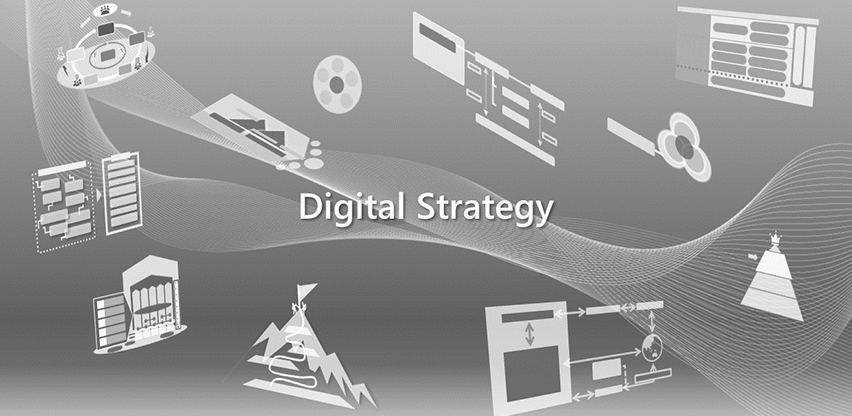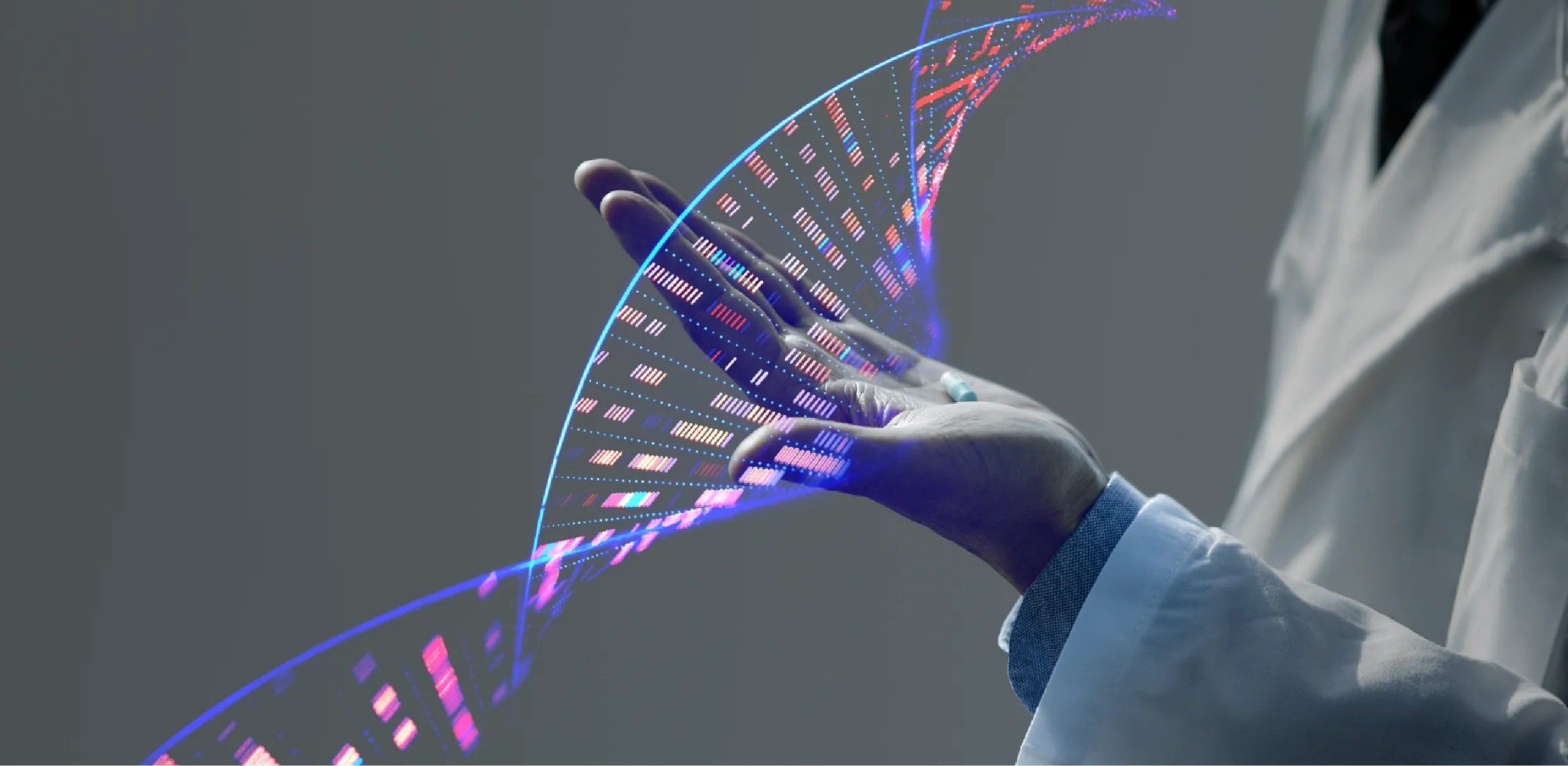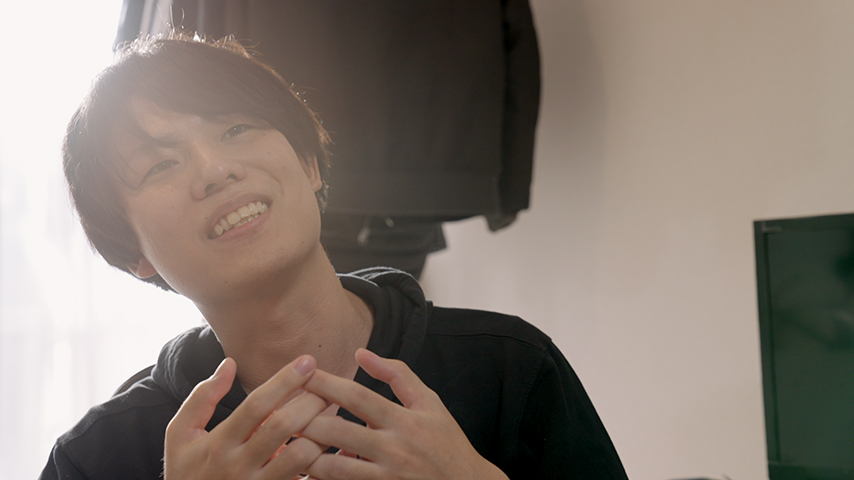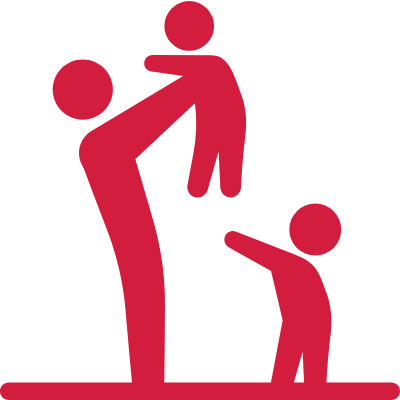あなたでないと、
創れない未来
を。
社外・学内イベント/セミナー情報
(2025/12/24現在)
今後弊社が出展する、2027新卒向けセミナーの一覧です。(日程確定分)
リストは随時更新されますので適宜チェックしてみてください。
・各イベントの詳細、対象(文系/理系、所属学科・専攻等)、参加方法等の詳細は、各イベントの主催者様にご確認下さい。
・諸事情により、変更や中止となることがあります。最新の情報は、各セミナーの主催者様からのご案内をご確認ください。
・下記以外に、各校OBOGの弊社社員が学内で独自に座談会等を開催することがあります。ご案内がありましたら、ぜひ奮ってご参加ください。
-
2026/1/11高専
セミナー名: 高専生のための仕事研究セミナー【東海・北陸地区】
開催場所: ポートメッセなごや 第二展示館 -
2026/1/13中央大学
セミナー名: 企業別卒業生セミナー
開催場所: 中央大学 後楽園キャンパス -
2026/1/15大阪公立大学
セミナー名: 2025年度 学内合同企業セミナー
開催場所: オンライン -
2026/1/20筑波大学
セミナー名: 企業研究会
開催場所: 筑波大学 大学会館 -
2026/2/8名古屋大学
セミナー名: 企業研究セミナー2026
開催場所: 名古屋大学豊田講堂(東山キャンパス内) -
2026/3/2電気通信大学
セミナー名: 2026年企業研究展示会
開催場所: 電気通信大学 西地区「体育館」
リコー自社イベント情報
(2024/11/18現在)
2024年11月以降に弊社が開催する、2026新卒向けイベントの一覧です。多くの方の視聴・参加をお待ちしております。
・各イベントの日時や対象(文系/理系、所属学科・専攻等)、テーマなどの詳細のご案内、及び予約受付はマイページにて行います。マイページ登録がお済みでない方は、ぜひ登録をお願いいたします。
・テーマ等は都合により変更になることがあります。
WEB会社説明
マイページでいつでも見ることができるオンデマンド動画です。まずはリコーの理解をこれで深めましょう!
MYPAGE登録・ログイン-
いつでも
(常時オンデマンド配信)対象者: すべての方
実施場所: オンライン(マイページ内)
社員とのオンライン座談会
複数名の若手社員と交流できる機会です。リコーのことや就活のことなど、気になっていることを質問をしてみましょう!
MYPAGE登録・ログイン-
2024/11/19(火)対象者: 回によって異なります。予約画面でご案内します。
実施場所: オンライン(Zoom) -
2024/12/5(木)対象者: 回によって異なります。予約画面でご案内します。
実施場所: オンライン(Zoom) -
2025/1/15(水)対象者: 回によって異なります。予約画面でご案内します。
実施場所: オンライン(Zoom) -
2025/2/18(火)対象者: 回によって異なります。予約画面でご案内します。
実施場所: オンライン(Zoom) -
2025/3/4(火)対象者: 回によって異なります。予約画面でご案内します。
実施場所: オンライン(Zoom) -
2025/3/5(水)対象者: 回によって異なります。予約画面でご案内します。
実施場所: オンライン(Zoom)
リコーのはたらくを知る1day
リコーの様々な仕事や事業所の様子を紹介!
リアルで、深く、リコーで働くイメージを具体化しましょう。
-
2024/12/17(火)対象者: 回によって異なります。予約画面でご案内します。
実施場所:リコーテクノロジーセンター(海老名) -
2024/12/18(水)対象者: 回によって異なります。予約画面でご案内します。
実施場所:リコーテクノロジーセンター(海老名) -
2024/12/19(木)対象者: 回によって異なります。予約画面でご案内します。
実施場所:リコーテクノロジーセンター(海老名) -
2025/1/9(木)対象者: 回によって異なります。予約画面でご案内します。
実施場所:リコーテクノロジーセンター(海老名) -
2025/1/10(金)対象者: 回によって異なります。予約画面でご案内します。
実施場所:リコーテクノロジーセンター(海老名)
RICOH Online Short Live!
「ESの書き方講座」や「あの社員に聞いてみよう」など、ちょっと気になるものごとを短時間でご紹介。ライブでは皆さんからの質問も受け付けます。
MYPAGE登録・ログイン-
1月~3月に月1回程度。
マイページで日程をご案内。対象者: すべての方
実施場所: オンライン(ライブ配信)
OBOG訪問システム(ビズリーチキャンパス)
弊社では、ビズリーチキャンパスに公式登録している社員へのOBOG訪問を受け付けております。
オンライン対応もございますので、社員に直接相談したい場合などにご活用ください。
・ご利用にはビズリーチキャンパスへの登録が必要です。
・ビズリーチキャンパス開設校の方が対象です。
・開設校であっても、出身社員が登録していない場合もあります。
登録社員の状況により、訪問受付を制限したり、お断りする場合がございます。予めご了承ください。
-
NEWS2025.04.04
2026卒の採用募集は終了いたしました。多くのご応募ありがとうございました。
Company
Company
リコーはコピー機の会社ではありません。
人とデジタルの力で、はたらく人やはたらく場をつなぎ、お客様の“はたらく”を変革する「デジタルサービス」の会社です。“はたらく”の進化の方向性を「ワークプレイスの拡がり」と「お客様価値の高まり」の2軸で定め、オフィスから現場、さらに社会へと価値提供領域を拡大しています。
オフィスや現場の情報をエッジデバイスでデジタル化し、そのデータを利活用するデジタル技術と共創プラットフォームで新たな価値を創造。それによってお客様の“はたらく”を変革し、持続可能な社会の実現にも貢献する―それがリコーのデジタルサービスです。
RICOH's Job
リコーの仕事を
覗く
80年以上、一人一人の想いや力を合わせながら、新しい価値を創ってきたリコー。
未来を創るためには何が必要か。
新しい価値を創ってきた社員たちが、それぞれの想いと経験を語ります。
People
People
リコーの社員を
知る
リコーで働く社員が大切にしていること、創ろうとしている未来、普段の働き方など、現場の社員一人一人がリアルな様子を語ります。
Documentary Movie
-
「入った会社では、人生は決まらない」~2年目エンジニア木田さん編
-
「はたらく歓びは『いい関係』の中にある」~10年目グローバルマーケティング中川さん編
Interview
-

お客さまの課題に寄り添い、技術で支える
グローバルSE/Radiniaina Tokinirina(ラディニアイナ・トゥキニリナ)(2019年入社)
- 理系
- 新卒
- 6年目以上
- 電気電子系
- 情報系
- 情報工学
Environment
Environment
環境と制度
仕事と生活の双方を自ら積極的にマネジメントし、そこで得られる充実感をエネルギー源に、より高みへチャレンジする。
そんな、リコーの目指すワークライフ・マネジメントを支える制度と実際の様子を紹介します。
-
リモートワーク主体勤務率
71.6%

-
男性育休取得率
97.6%

-
有休平均取得日数
16.1日

Recruit