特別対談 「未来は分からない」と言える企業は強い。リコーが始めた「面白い種まき」とは
- イノベーション

※Written by BUSINESS INSIDER JAPAN ※所属・役職はすべて記事公開時点のものです。
「企業にとって大きな変化を遂げるための「イノベーション」が求められるようになり久しい。だが、言うは易し行うは難しで、多くの企業が試行錯誤し続けている。
一方で、小説や映画に代表されるSF(サイエンス・フィクション)作品で描かれた未来が実現されている実例は非常に多い。SFのような架空の世界の希求こそが、人類を未来へ導くひとつの道筋であることは間違いないだろう。その視点から「SFプロトタイピング」という手法をビジネス現場で広めているのが宮本道人氏だ。リコーの10年後の未来を描くMIRAIプロジェクトのリーダーである小野政亮氏とともに、イノベーションを起こし、未来をつくるプロセスを語っていく。
SFプロトタイピングでは、フィクションのように未来を語る
未来を描くうえで、難しいのはどのような点でしょうか? SFプロトタイピングでは、それをどのように解決していきますか?
小野政亮氏(以下、小野): リコーの未来像を描くために立ち上がったMIRAIプロジェクトで、国内外の社内メンバーと何度もブレストを繰り返しました。でも、みんな似たような未来を描きます。一体感があるとも言えますが、意外性がない。未来を描く際に、現在にとらわれてしまうのが難しい点だと思っています。
宮本道人氏(以下、宮本): まさにそれを打破するのがSFプロトタイピング、ということになりますね。簡単に説明すると、みんなでフィクションをつくったり、語り合ったり、未来像を共有したり、議論したりしていく、という手法です。
ありがちなのが、新しい取り組みをしようにも「無難なもの」を選んでしまうこと。失敗したら責任を取らなくてはいけないかもしれないし、メンツも保てない。でも、「SF」をベースにすれば飛躍した考え方ができます。
僕がワークショップを実施する際は、40年後の未来を想像してもらうことが多いです。そこから「バックキャスト」という、描いた未来から逆算して今何をすべきか導くプロセスを踏むことで、今の延長線上にはないアイデアが具体的に描けます。
バックキャストとフォアキャストは分けて並行で実施する
小野さんが取り組んでいるMIRAIプロジェクトには、宮本さんも参画していると伺いました。MIRAIプロジェクトでは、どのような取り組みをしているのでしょうか。
小野: MIRAIプロジェクトは、2022年の8月下旬からスタートしました。リコーが中長期の戦略を策定するにあたり、今まで培ってきたものづくりや、MFP(多機能プリンター・周辺機器)における10年後の未来を描くプロジェクトです。通常、企業で3~5年ほどの機種ロードマップを描くと、「既存商品のバージョンアップの繰り返し」のような企画になってしまう。既定路線を壊して未来を描くことが我々のミッションです。
MIRAIプロジェクトでは、3つのサブプロジェクトを並行して走らせています。外部からアイデアを募るオープンイノベーションコンテストや、デザイン思考を活用して、現実から未来を考えるフォアキャストのプロセスもあります。そしてもうひとつが、宮本さんにお願いしているSFプロトタイピングのプロジェクトです。

宮本道人(みやもと・どうじん)氏
東京大学VRセンター特任研究員、科学文化作家、SFコンサルタント、博士(理学、東京大学)
1989年生まれ。科学技術、エンタメ、社会の開かれた関係を築くべく、研究、創作、ビジネスに取り組む。単著に『古びた未来をどう壊す?』、編著に『SF思考』『SFプロトタイピング』『プレイヤーはどこへ行くのか』など。フィクションを用いた未来共創メソッドを開発し、多数の企業でワークショップを実施している。
宮本: 3つのサブプロジェクトに分けているのが素晴らしいと思います。多くの企業では複数の企画を分けられず、闇鍋状態にしてしまう。SFプロトタイピングは、短期的成果よりも長期戦略を重視するものなのに、最初からフォアキャストの考え方を混ぜ込んでしまうと、凡庸なアイデアに落ち着いてしまいがちだという点に留意すべきなんですね。
小野: 一方で、オープンイノベーションコンテストも実施し、社外に広く一般公募しています。内容は、学生やイノベーターを中心とした500万ユーザーが登録するプラットフォームを使ってMFPの未来の可能性を募集。募集テーマは4つのカテゴリーを用意しました。「紙を必要とする世界」「ペーパーレスの世界」はフォアキャスト。これらに対して、宮本さんと考える「SFプロトタイピングの結果として生み出された未来の世界」はバックキャストです。さらに、その3つのどれにも属さないカテゴリーとして「ワイルドカード」もあります。
宮本: SF的な未来を考えたうえで、そこにつなぐ導線をいくつも用意していますよね。社内だけでなく、学生など若い世代に向けてもアイデアを募集している。そこまで立体的に設計できているのは、SFプロトタイピングをひらめきだけで終わらせない最高の環境といえます。
SFプロトタイピングに不安は付きもの
SFプロトタイピングを進めるうえで、注意すべきことはどのようなことでしょうか。リコーさんの社内では、それをどう実現されていますか。
宮本: SF的な未来からバックキャストしていくときに、フォアキャストで得られる安心感に惑わされないことが大切です。既存の自社リソースとすぐ繋げたいという欲望にじっと耐え、40年後から10年後が見えてきて初めて、今やるべきことを考えるのがコツです。分かっていても、プロジェクトの途中で上層部からアウトプットを求められてフォアキャストに逃げた結果、ありがちな未来しか出てこない、というパターンが多いので。
比喩としての余談なのですが……。僕、AGA(薄毛)治療を最近始めたんです。でもこれ、人によっては最初の1カ月くらい、逆に古くて弱い毛が抜けていくんですね。このタイミングで見ると「治療の効果ないじゃん」と思ってしまう。でも、それこそが新しい毛を生やすためのカギで、6カ月後に見たら、「効果があったね」と誰しもが思ってくれるはずです(笑)。
小野: 「途中で結果を出せ」と言われても……(笑)。
宮本: 無理ですね。むしろ若干マイナスに見えるかも。

小野政亮(おの・まさあき)氏
リコーデジタルプロダクツ 海外マーケティンググループリーダー
1999年にリコーへ入社後、首都圏や東北にて国内市場向けの商品担当を務める。2008年に海外ビジネスへ転向、海外向けMFP商品担当を経た後、2010年より米国駐在。駐在期間中は米国市場のマーケティング、ディーラービジネス戦略を担当、海外においても現場主義を実践した。2019年より現職。2022年夏に発足した、未来のMFPを検討するMIRAIプロジェクトのリーダーとなり、複数のサブプロジェクトを束ねている。
小野: 周囲の理解促進についてはメールでの活動報告やSNSでの情報発信など「草の根運動」をしています。個人的に説明していると、応援の声や有用な情報がもらえることもあります。今朝もアメリカから「こういうやり方もある」と連絡をもらったばかりです。
宮本: ほかに、SFプロトタイピングでは、多様性が大事だと考えています。ある会社では、多様性を重視したメンバー選びをお願いしたのに、全員60代理系男性だったことがありました。博士号を取った分野が違うから「多様」だと言われたんですが、これで会社の未来を考えたら絶対いろんな視点や配慮が欠ける結果になりますよね(笑)。その点、リコーさんはバランスを調整していらっしゃいました。
小野: 私たちは、年代やジェンダー、専門性なども多様になるようにしています。入社2~3年目でも、ワークショップで忌憚ない意見を出してくれています。ワークショップで出てきたガジェットのアイデアは3つあります。
ひとつは「解像度オニオンスキン」で、情報伝達をするときに、解像度が高すぎても低すぎてもロスが大きいから、解像度を自由に選別してやりとりできるツールです。ほかに、「報連相ゲーム」は、仕事で不可欠な報告・連絡・相談が楽しくなるゲーム。「アンリミテッド自販機」は、企業内でスキルやモノを気軽に売り買いできる自販機。それらのガジェットがある世界を想像して、その中で未来のMFPの役割を考えていきます。
ただ、ここからリコー自身の未来をどう描くか、まだ不安はありますね。
宮本: SFプロトタイピングのミソは、むしろ「本当にソリューションが出てくるのか不安」という状況をあえてつくるところにあります。簡単に解決策に直結するアイデアだったら、ありがちなものにしかならないですから。ロボット工学を専門とする金出武雄さんは、「素人のように考え、玄人のように実行せよ」と言っています。
多くの企業は、最初に有識者を集めて意見を聞いて、分かった気になり安心し、その後は勉強を継続せずにプロジェクトを進めます。でも僕の考えでは、最初は思い切り妄想し、途中から有識者に助言をもらって玄人として実行していく、という順番にすべきです。不安は、自分が安牌に逃げていない証拠として捉えると良いと思います(笑)。
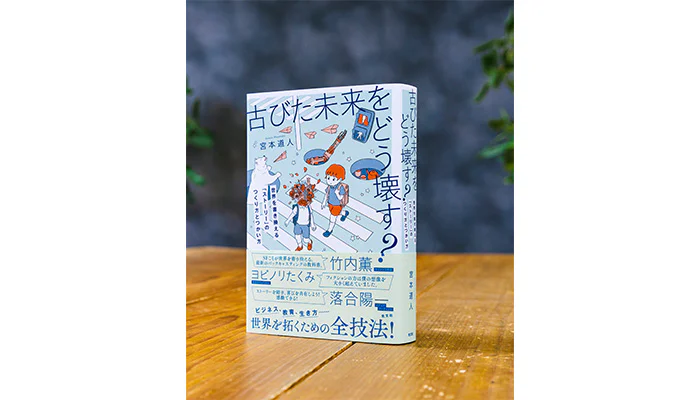
宮本氏の初の単著『古びた未来をどう壊す? 世界を書き換える「ストーリー」のつくり方とつかい方』(光文社)
これからは、みんなで意見を出し合える世の中に
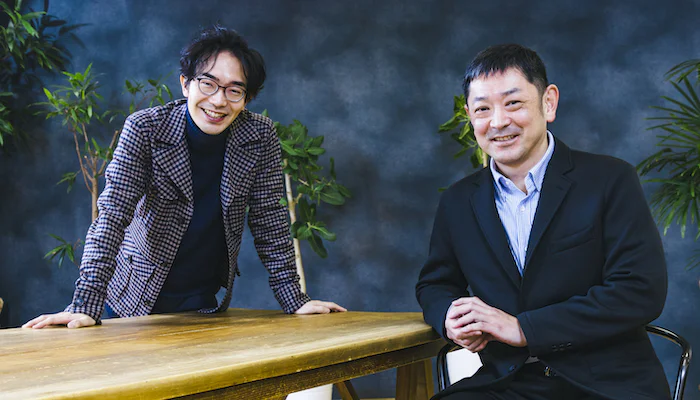
今後のMIRAIプロジェクト、今後の企業活動のあるべき姿について、お二人の考えを教えてください。
小野: MIRAIプロジェクトについては、まだ3つのサブプロジェクトから落とし込む方向性が見えていない段階ですが、商品性、社会背景、働き方といった大切にする世界観を明確に決めたうえで、1カ月ほどかけて練り込んでいきたいと考えています。
宮本: 「未来が見えていない」と言える企業は強いですよね。「わが社は未来を見据えている」と多くの企業は言いますが「そんなわけないじゃん」と僕は思います。未来共創プロジェクトに大量に携わってきた経験から言うと、やればやるほど未来は分からなくなる。ただ「未来のどこが未知なのか」の解像度は徐々に高くなり、そこから逆説的にやるべきことが見えてきます。
小野: 「分からない」といえば、お客さまのニーズも昔と変わってきているのを感じます。それにより、販売会社などお客さまに対峙する人たちも変化している。だから、高性能な商品を開発するだけでは売れません。
細かなニーズ、つまり多様性が求められています。それらを早くキャッチしてフィードバックする仕組みづくりはマストだと思っています。
手前味噌ながらリコーには技術はあります。高機能なハードウェアを出すだけでなく、デジタルサービスを提供する会社のエッジデバイスとして、お客さまに寄り添える商品を提供したいですね。
宮本: 人の変化を見るというのは、誰もが自由に未来を語り合える社会の実現にも繋がります。「素人」のアイデアが未来をつくっていく。そして、その環境を整えるのが「玄人」の役目です。「自分だけが楽な道」は選択しない、という覚悟が、企業の未来を左右するのだと思います。











