トップメッセージ
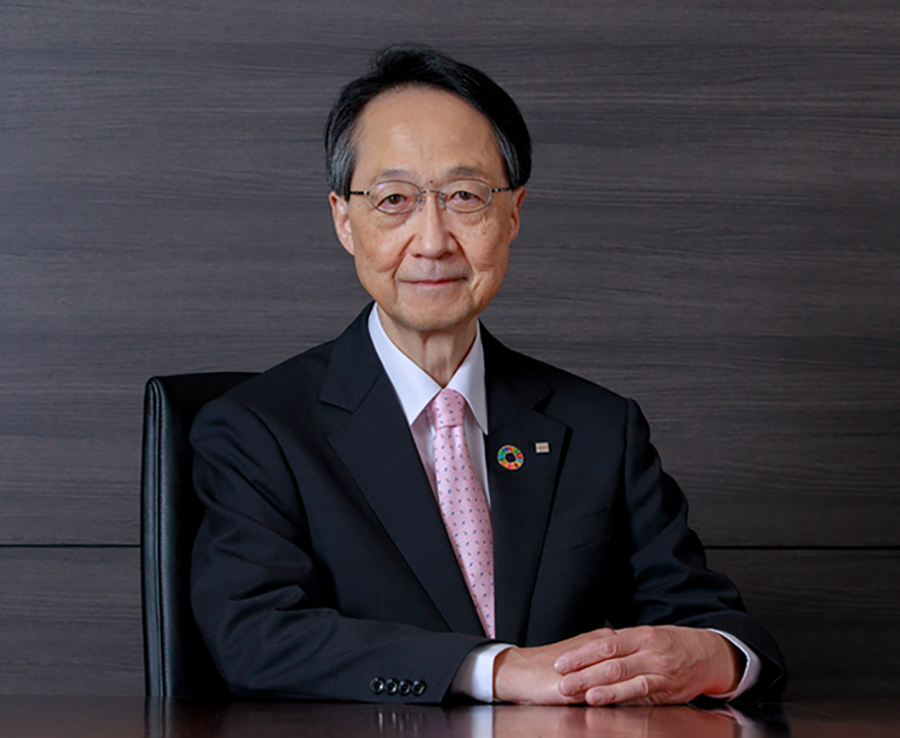
“はたらく”に寄り添い、
お客様の生み出す力を支える
デジタルサービスの会社へ
大山 晃
代表取締役
社長執行役員・CEO
1986年 7月
株式会社リコー 入社
海外向けOEMおよび国内販売会社での営業に従事
その後、欧米で買収した企業のPMIなどに携わる
2011年 4月
RICOH EUROPE PLC 社長・COO
2012年 8月
株式会社リコー グループ執行役員
RICOH EUROPE PLC CEO
2014年 4月
常務執行役員
コーポレート統括本部 本部長
2015年 6月
取締役
2016年 6月
専務執行役員
2017年 4月
CFO
2021年 4月
コーポレート専務執行役員
リコーデジタルサービスビジネスユニット プレジデント
2021年 6月
取締役
2023年 4月
代表取締役 社長執行役員 CEO(現在)
2023年9月6日
多様性と自律性でリコーを信頼される企業へと成長させる
2023年4月に代表取締役 社長執行役員・CEOに就任した大山晃です。経営トップとして、これまでにない大きな責任を担うことになり、身の引き締まる思いです。
また4月には企業理念「リコーウェイ」を改定し、「“はたらく”に歓びを」を使命と目指す姿に位置付けました。この実現に向け、はたらく人に寄り添い、はたらく人の生み出す力を支える「デジタルサービスの会社」への変革を加速していきます。
私はCEOとしてリコーの企業価値を向上させ、未来につないでいくことを自身の使命ととらえ、株主、社員やその家族、お客様やお取引先、社会など、すべてのステークホルダーに絶大なる信頼をいただける会社を目指し、まい進する所存です。
私自身のキャリアを振り返ると、海外、特に欧米に身を置いた期間が長く、組織運営における多様性の大切さを身に染みて実感しました。その中で、私が重視してきたのが人との対話、コミュニケーションです。国や地域が違えば言葉や文化が異なります。欧州駐在時にはそうした異なるバックグラウンドを持った者同士が融合し、それぞれの個性や異なる意見を汲み取りながら、多様な考えを尊重し合うことで、新たなシナジーを生み出すカルチャーを醸成してきました。同質化した組織は進化しません。「デジタルサービスの会社」への変革を実現するため、社員の多様性を尊重し、一人ひとりの自律的な成長を支援することでさらなる挑戦を促し、それが事業成長へとつながるよう、マネジメントを行ってまいります。
“はたらく”の環境変化を先取りし、事業機会につなげる
コロナ禍以降、世界は目まぐるしいスピードで変わり続けています。社会情勢に加え、はたらく環境や、はたらく人を取り巻く状況や意識そのものも加速度的に変化しています。ハイブリッドワークがグローバルトレンドとして定着し、仕事はオフィスだけでするものという概念がなくなりつつあります。オフィスが担う役割も、単に「仕事をするための場所」から「創造性を醸成するための場所」へと見直されてきています。
加えて、生成AIの登場などAIの進化は目覚ましく、それに伴い、はたらく人に求められる価値も急速に変わってきています。
さらに、はたらく人自身の考え方にも変化が見られます。はたらく目的は収入を得るという経済的なニーズに加え、仕事を通じて得られる「充足感・達成感」という心理的なニーズがありますが、最近は心理的側面により重きを置くようになってきたと思われます。多くの場合、この「充足感・達成感」は、人が何かを生み出した時、価値を創造した時に得られるものです。したがって、この創造性を高めることが、ますます重要になってきていると考えています。
こうした環境変化に対して、非常に大きな可能性を感じるとともに、リコーがデジタルの力ではたらく人の生み出す力(創造力)を支え、その先に持続可能な社会があるという、目指すべき方向は間違っていないと確信しています。
20次中計:改革を断行し、「デジタルサービスの会社」への助走を完了
第20次中期経営計画(20次中計)では、「デジタルサービスの会社」への変革を掲げ、買収を含む成長投資を進めながら、経営基盤の強化に向けて、組織や制度、ITシステムなどの社内改革も推し進めました。2021年4月に社内カンパニー制を導入し、各ビジネスユニット(BU)への権限委譲を進め、各BUがそれぞれの市場で起こる変化に迅速に対応できる体制を構築しました。加えてROIC経営や事業ポートフォリオマネジメントにより、収益率向上や体質強化に向けた取り組みも加速しています。さらに、戦略実行力の強化を目的に、2022年4月にリコー式ジョブ型人事制度を導入するなど、人的資本に対してもさまざまな取り組みを進めてまいりました。一方で、世界的なサプライチェーンの混乱により、複合機を中心としたデバイスの供給が滞り、業績に影響を与えるなど、この数年は外部環境変化への対応に追われました。
最終年度である2022年度の業績は、売上高が当初目標を上回る21,341億円と増収となりましたが、プリントボリュームの回復遅れやハードウェアの部材不足、原材料価格の高騰などの影響によって、営業利益は当初目標を下回る787億円、ROEも目標に届かず5.9%となりました。一方で、社会課題解決に向けた取り組みを着実に推進し、世の中からも高い評価をいただくことができました。リコーでは、ESGの取り組みを「非財務」ではなく、事業における将来のリスク回避・機会獲得につながる「将来財務」と位置付けて活動しています。今後もESGを推進し、持続可能な社会の構築に貢献することが事業成長につながるという、リコーグループの同軸経営の考え方を実践していきます。
21次中経:3つの基本方針でグループグローバルのシナジーを発揮

2023年4月から「デジタルサービスの会社」として着実に成果を生み出す「実行」の3年間となる、第21次中期経営戦略(21次中経)がスタートしました。21次中経では、3つの基本方針として「地域戦略の強化とグループ経営の進化」「現場・社会の領域における収益の柱を構築」「グローバル人材の活躍」を掲げ、最終年度の2025年度には、営業利益で1,300億円、ROE9%超の達成を目指します。
1つ目の「地域戦略の強化とグループ経営の進化」でのポイントは、デジタルサービスのストック収益を積み上げ、収益性を向上させることです。デジタルサービスの売上高比率を現状の44%から60%超へと引き上げ、収益構造の転換を図ります。そのためにも、顧客接点における価値創造能⼒の向上、リコーグループ内でのシナジー発揮、環境変化への対応⼒の3つが重要になります。これらの取り組みは、収益⼒の強化、ひいては企業価値の向上につながります。
2つ目の「現場・社会の領域における収益の柱を構築」では、デジタルサービスの領域を拡げ、より幅広いお客様に価値を提供していくため、現場領域の事業拡大と社会課題の解決に直結するビジネスの創出に取り組みます。注力する事業領域を見極め、現場・社会の領域における収益の柱を構築していきます。
3つ目の「グローバル人材の活躍」では、成⻑領域への人材シフトとグローバルでの人的資本の価値の最大活用を図ります。社員の成⻑と事業の成⻑を同時に実現し、稼ぐ力を向上させます。
これらを確実に実行することにより、収益性を向上させ、さらなる企業成長を実現させます。
リコーならではのデジタルサービスで新たなストックビジネスを確立
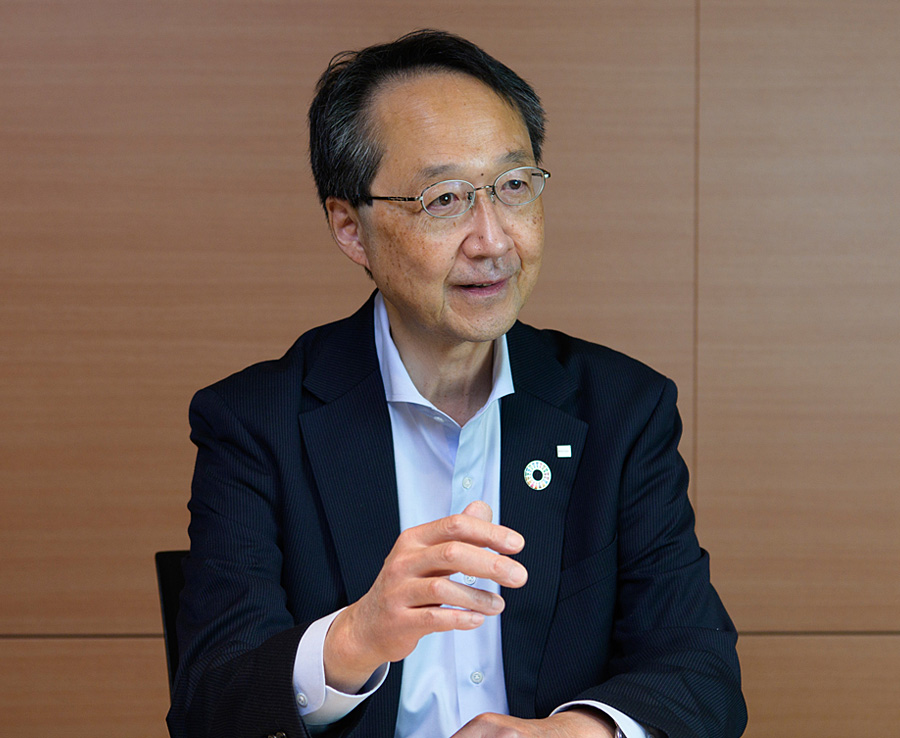
基本方針の1つ目「地域戦略の強化とグループ経営の進化」のポイントである、デジタルサービスのストック収益の積み上げについてご紹介します。
リコーのプリンティングビジネスは、複合機の販売というフロー(売り切り型)ビジネスを起点に、印刷に伴う消耗品販売やお客様先での保守サービスなど、利益率の高いストックビジネスにより安定的な収益を確保してきました。今後はデジタルサービスの会社としての成長を確実なものにするため、プリンティングビジネスに加え、新たなストック収益の創出を加速させます。お客様の課題に合わせたさまざまなデジタルサービスを提供し、デバイスやIT環境のサポート・サービスや、SaaSベースのアプリケーション・サービスなどのストックビジネスを成長させ、地層のように収益基盤を積み上げていきます。
デジタルサービスの市場には高い成長性があります。その中で、複合機に代表されるデバイスを通じてグローバルに広がる顧客ネットワークは、私たちの大きな強みです。文字や写真、音声・動画など、人が認知可能なアナログ情報と機械・ソフトウェアが処理するデジタル情報の出入り口となる独自の優れたエッジデバイスを、リコーグループは多数保有しています。これらのエッジデバイスと、自社やパートナーのさまざまなアプリケーション・サービスとをRICOH Smart Integration(リコーグループ共通のプラットフォーム)上で融合し、お客様の“はたらく”のDXに貢献します。特に中堅・中小企業のお客様の場合、自社内にITの専門性を持つ人材が不足しているため、専門性を持った体制によるサービス・サポートが不可欠となります。この点において、業界随一の販売・サポート体制でお客様に寄り添い続けてきたリコーだからこその強みがまさに活きてくる、また市場優位性につながる領域であると確信しています。
デジタルサービスの提供能力を強化するために、グローバルで買収や業務提携を着実に進めています。2022年度には業務用スキャナーで世界No.1のシェアを持つ株式会社PFUをリコーグループの一員に加えました。2023年5月には、2024年度前半をめどにリコー、東芝テック株式会社両社の開発・生産に関する技術的な強みを持ち寄り、合弁会社を組成することを発表しました。デジタルサービスの提供には、競争力のあるエッジデバイスが欠かせません。リコーグループやパートナーの技術やノウハウを掛け合わせ、シナジーを創出することで、競争力の高い、強いものづくりを実現していきます。また、ワークフローのデジタル化領域を広げるため、2022年度にサイボウズ株式会社と業務提携し、RICOH kintone plusを日本や北米で展開するなど、アプリケーションの拡充を進めています。さらに、デジタルサービスの提案能力を強化するためのデジタル人材教育にも力を入れています。
「はたらく歓び」で社員と事業の成長を同時に実現

入社3年目の社員と実施したラウンドテーブルの様子
私は社員の成長が企業成長の原動力であると考えています。20次中計では、デジタル人材の育成・強化など、人材に対してさまざまな取り組みを推進してきました。これは、人が持つ能力やスキルを資本としてとらえ、適切な投資をしていくという、人的資本の考え方に基づいています。デジタル人材の教育制度の拡充、グローバルでの人材活用など、チャレンジの機会を積極的に提供することで社員の自律と成長を促し、社員自身が「はたらく歓び」を実感できるような企業風土を醸成していきます。「はたらく歓び」を感じることが社員の成長の新たな原動力となり、そのサイクルが回ることが、企業の持続的な成長には不可欠だと考えています。グローバルでの社員エンゲージメント調査結果を見ると、「デジタルサービスの会社になるためにどういう貢献をしているか」という設問に対して自分の貢献や社会に対する寄与を具体的に説明できる、つまり、変革を自分事としてとらえて実行できる社員が確実に増えてきています。社員一人ひとりのパフォーマンス最大化を通じて、個人と事業の成長を同時に実現してまいります。
資本市場に対しては、当社が目指す「デジタルサービスの会社」に向けた道筋をより分かりやすくお示ししつつ、数字として結果を出していくことが必要と認識しています。将来にわたってキャッシュ・フローを増大していけると確信いただけるよう、デジタルサービスの領域での実績を積み上げていきます。上場会社としてPBR1倍は最低限の達成水準との認識から、社長就任後すぐに、PBR1倍以上を実現するためのプロジェクトを立ち上げ、活動を開始しました。まずは、自社でコントロールできる指標として株主資本利益率(ROE)と1株当たり当期純利益(EPS)の安定的な向上に向けて、利益成長をベースとしながら、リコー式ROICツリーの活用を通じた資本コスト経営の徹底と、株主還元を含めた資本政策を重視していきます。将来財務と位置付けるESGの取り組みにおいては、トップランナーとして世界をリードしていきます。
リコーは、5年先、10年先にも、お客様の生み出す力を支え続け、お客様に「はたらく歓び」を感じていただける企業を目指します。これからもお客様に寄り添い、社会から愛され信頼される会社に向けて、成⾧の道を歩んでまいります。