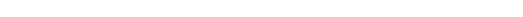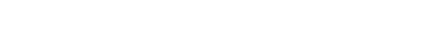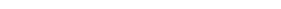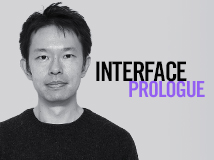倉田タカシ×INTERFACE
ストーリー3/3
うつろいながら、あたらしさへ:倉田タカシ
December 18, 2015
SF作家・倉田タカシさんが想像する、2036年の「インターフェイス」を全7回(短編小説4本+対談記事3本)にわたって紹介。短編小説の本編(3/3)となる本記事。『紙のオフィス』に閉じ込められた原因は判明したが、依然、脱出方法が見つからない3人……。だが、佐々波は自身のかばんの中に、あるモノのプロトタイプがあることを思い出す。
古いロジック、新しいロジック
毎日、新しく作られる環境によって、
より徹底的で、根本的な「刷新」を体験しつづけること。
すべてがインタラクティヴなオフィス、
すべてがテンポラルでディスポーサブルなオフィス。
〈紙のオフィス〉のキャッチコピー案だ。
新しいアイデアを模索する闘いは、自分の中にもある、古いものとの闘いでもあった。
戸見は早口で説明する。
「僕がさっきの折り紙コードで獲得できたのは、〈パペル・ノヴァ〉のオフィス構築システムにおける、この特定のワークスペース内での上位権限でしかないんですよ。でも、セキュリティ保護の原則を外すには、さらに上のレベルが必要で……」
佐々波は口の端をあげ、うなずく。
「あの折り紙は、本当の意味での〈裏口の鍵〉じゃなかったってことね」
戸見はしゃがみこんで唸り、床をにらむ。
「しまったなあ……予想すべきだった」
人間そのものが、部外秘の情報として〈紙のオフィス〉のシステムに認識され、携帯メモリと同じように持ち出しを禁じられている。だから出られないのだ。
「オフィスが気を利かせすぎちゃったんだな」と吉田が笑う。
通常、ワークスペースの中では情報の流動性を極限まで高めている。つまり、どれだけ〈紙〉に出力しても、どれだけコピーを作ってもかまわない。〈パペル・ノヴァ〉は、消すことを前提においたメディアだ。
かわりに、データを外へ持ち出すことには徹底的な制限を設けている。携帯型メモリなど、〈パペル・ノヴァ〉以外の記録メディアにデータを移したら、そのメディアを持って部屋から出ようとしても、ドアが開かない、ということになる。
一方、この技術を〈都市のインフラ〉として展開するために戸見がシステムに付け加えた機能においては、個々の人間を情報の集合体として扱う。
ただ情報を受け取って処理するだけの存在だったユーザーを、それ自体も一種のデータベースとして扱う形に拡張したのだ。
「古いのと新しいのと、ふたつのロジックがぶつかっちゃってるわけだ」
そうですね……そうなんですよ。戸見は吉田に答え、しゃがみこんだまま、なかば声に出しつつ、修正案を頭のなかで組み立てていく。
どこがぶつかってるかはわかった。回避はそんなに難しくない……1日あれば対処できる……うん。うん。よし。
立ち上がった戸見は、さっぱりとした顔で2人を見た。
「じゃ、壊しますか」
佐々波が目を丸くして、
「えっ、いいの……というか、壊せるの?」
「さすがに、おとな3人がかりで壊せないほど頑丈じゃないですよ」
「でも、壊しちゃったらまた2日かけて作り直しでしょ?」
吉田は考え込む姿勢で、
「壊すのは大好きだけどさ、多分、なんかほかに手があるよ。まだ付き合えるから、考えようよ」
「そうだ! 待って、これ使おう」
佐々波がかばんを探り、一枚の紙片をとりだした。
戸見が驚いて顔を寄せる。
「まだ持ってたんですか、それ」
実用化には至らなかった、〈スマート紙幣〉のプロトタイプだ。〈パペル・ノヴァ〉の企業が試験的に開発したが、紙のお金という概念が無意味になりつつあると結論がでて、とりやめになったのだ。
通常の〈パペル・ノヴァ〉とは違い、この紙のなかには計算能力の高い薄片プロセッサが漉き込まれている。
つぎに佐々波は、小さなポーチを取り出し、中から大き目の錠剤をひとつ摘みだす。
それを口に入れ、まずそうに噛み砕く。ちょっとごめんね、と言って後ろを向くと、子どもがアイスの蓋を舐めるように、スマート紙幣の片面を丹念に舐めた。
行儀わりいな、と大笑いする吉田を軽くにらんで、
「しょうがないでしょ、水持ってきてなかったんだから」という。
いま舐めたほうの面を壁に貼りつける。
すると、貼りつけられた壁面の〈パペル・ノヴァ〉が反応し、紙幣の脇から、四角い泡のように入力のウィンドウが膨らみ、活性化した。
「バインダーですか」
「そう、ボランティアグループで使ってるやつ」
佐々波が口にいれた錠剤は、〈パペル・ノヴァ〉の繊維をまとめているものと同じ機能性素材だ。それを唾液で溶かして、信号を伝えられるようにしたのだ。壁の紙に貼りつけられた紙幣は〈紙のオフィス〉と一種の交渉をし、通信を確立した。
「じゃ、おねがいします」佐々波が後ろに下がり、戸見に一礼する。
ありがとうございます、と戸見もかしこまってから、目の前にひらいたメニューを見つめる。佐々波のつかった仕掛けは、もうすこしだけ高いレベルでの操作を可能にしてくれていた。
あいかわらず、セキュリティ規制に反して扉を開かせるだけの権限はない。かわりに、ひとつ出来ることがある。
戸見は自分の認証コードを打ち込み、メニューからそれを選ぶ。
〈紙のオフィス〉のデモンストレーションが始まった。
紙のむこうへ
円筒形をした内壁は、たくさんのウィンドウを重ねて並べ、それぞれに風景やオフィス活用のイメージを表示していた。いま、それがひとつながりの大きなスクリーンになり、輝く。
たてつづけに映像があらわれる。
障子に指で穴を開け、外を覗く子ども。
紙でつくったお面、からくりがしかけてあり、表情がかわる。
あぶりだしで現れる、拙く大きなひらがな。
短冊に書かれた願い事が風に揺れる。
授業中にそっと手渡される、ノートの紙片を畳んだ手紙。
紙に文字の書かれるイメージ。
羽根のペンで、鉛筆で、タイプライターで、インクジェットで……
たくさんの紙片が天井から舞い落ちてきて、そこにも同じ映像が表示されている。
映像に〈パペル・ノヴァ〉があらわれる。
春の嵐のようにオフィスを紙片が舞い、働く男女のまわりを吹き抜ける。
それらの紙片が、街へ飛び出していく。
円筒形をした〈紙のオフィス〉の、入り口とは逆の端へ向かって、映像が流れていく。
輝く紙片の群れは形を変え、街のなかでそれぞれの役目を与えられる。
情報をもたらし――手首に巻かれて混雑のない通り道を知らせ、
仲立ちをする――祭りの広場で団扇として配られ、異国の客に言葉を通訳する。
そして、紙の形から解き放たれる。
人と人のあいだに浮かぶ形のない界面となって、意識にのぼらぬ舞台で仕事をする。
人々の営みが、この流動するインターフェイスによってほぐされ、繋がっていながら縛られない、まとまりつつも自由な形の、移ろいによって調和を保つ社会がつくられる――
奥の壁はいつのまにか開き、夜間照明に照らされた展示場が見えていた。3人の視線の先には、理想化された都市の模型がある。本番ではこれが輝いて観客を迎えるはずだ。
戸見は大きく息をつき、佐々波と吉田は拍手する。
佐々波が低い声でつぶやく。
「こういうふうにしていかなくちゃね、現実も」
「三割くらい実現できりゃ、大満足だなあ、おれは」と吉田。
「遅くまで拘束しちゃってすいません。詰めが甘かったです」
恐縮する戸見を、吉田がねぎらった。
「年内に大きなバグ出しができて、よかったじゃん」
戸見はため息を吐いた。
「なんか、まだまだですね……。佐々波さんや吉田さんのやってることになかなか追いつけない」
「戸見くんのやってることが一番重要なんだよ」
佐々波が励ますように言う。
「基礎があってこその応用なんだから。ボランティアグループがやってこれたのも、戸見くんの会社がこの技術を開発して、かつ、それを安く提供できるようにして、全国に設備を普及させられたおかげだもの。それだけの力が企業にあったからこそ、状況を変えられたんだよ」
現実離れしてると言われるかもしれないけど、と佐々波は前置きして、
「人類の歴史で初めて、本当の意味で〈善〉が勝つ時代がやってくるのかもしれない、と思ってみてよ。'36年が、そのはじまりの年として記されるかもしれないんだよ。そう思うとわくわくしない?」
吉田のニヤニヤ顔が、苦笑のほうにちょっとずれる。
「おれはなあ……そういうのを簡単には信じない星の出身だから。でも、そうしたいよね」
「力を貸してくれますよね?」
佐々波が期待のまなざしを向ける。
「貸してますとも」
吉田は鷹揚にうなずいた。
「戸見くん。善い人でいてね。いままでより大きな力を使えるようになっても、そこは変わらないでいて」
佐々波の言葉に、戸見は小さくうなずく。向かい風に踏ん張るように足をひらき、ポケットに両手を突っ込んだ。
「僕は、自分の考えに忠実にやっていきますから。そこはぶれないんで、安心してください」
戸見の頭のなかでは、年明けからとりかかる改修のプランが走り出していた。
これで行けるという確信はある。自分はこれを扱える。作っていける。
展示場の自動ドアが開くと、冷たい外気と、年の瀬の喧騒が押し寄せた。
佐々波は耳のうしろの情報端末に指をやり、夫との通話をひらく。
「ふたりはいい子にしてた? うん、これからちょっと飲んで帰る。ありがと、じゃあね」
海辺で花火が上がっている。時刻表示は、ゼロ時零分。
あたらしい年だ。
「じゃあ、わたしが奢るから」
「いや、ここは僕の奢りでしょ!」
「おれは1円も出さなくていいかな?」
「なんでもいいよ、パッと飲んでパッと帰ろう!」
そういって佐々波が端末に指示すると、道のすこし先に無人タクシーが止まる。
そして3人は――走った。
吉田を先頭に、拳をつくって両手を振り上げ、勝利の叫びをあげながら、通行人のあいだをいっきに駆けぬけ、車に飛びこんだ。
PROFILE
-

-
倉田タカシ(クラタタカシ)作家
1971年、埼玉県生まれ。東京都立大学(現 首都大学東京)2部・工学部電子情報科を中退し、イラストレーター・漫画家の活動と並行して、WEB系教材制作会社に勤務。その後、フリーのWEB制作業を経て、2010年にSF作家としてデビュー。2015年、第2回ハヤカワSFコンテストで最終選考に残った作品『母になる、石の礫で』が初長編として刊行された。
-

-
ざいん(ザイン)イラストレーター
エッジの効いた空間演出とポップなイラストの妙が、国内外から高い評価を受けているイラストレーター。米TOYOTAの広告で初音ミクのコラボイラストを描いたほか、『謎解きゲームCD 真・女神転生 明ケナイ夜カラノ脱出』や『ATLAS・EXIT TUNES』のジャケットイラスト、ライトノベル『されど罪人は竜と踊る』の表紙・挿絵など、幅広いシーンで活躍している。