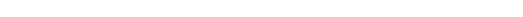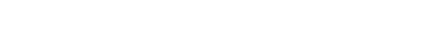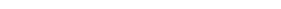柴田勝家×EDUCATION
ストーリー2/3
水のように:柴田勝家
October 8, 2015
SF作家・柴田勝家さんが想像する、2036年の「教育」を全7回(短編小説4本+対談記事3本)にわたって紹介。短編小説の本編(2/3)となる本記事。水を利用した、未来の社会インフラ基盤「液相コンピューター」。水の流れのように情報が移動し、文化が形成される時代にあっても、生徒と教師の変わらぬ日常があった。
教育インフラ
教育の場は、今や社会の全てに移管された。その基盤になったのが液相コンピュータのインフラで、僕の本業は水道局員としてそれのメンテナンスを行うことでもある。
その日も僕は、街中に溢れる広告用水盤の保全作業に従事する。そこに映る拡張ホロは、水の中に溶け込んだ分子トランジスタに記録されながら、こちらのデバイスに反応して絶えず変化している。手をかざしてみれば、広告の詳細情報が問題なく手元のデバイスに送られてきた。
大容量メモリ、そして光情報の伝送路となった水は、今や全国の水道を通っている。かつて電話回線が担ったネットインフラの役割を、今では別のインフラが担当しているのだ。
水資源の豊富な日本だからこそ達成できたインフラ。蛇口を捻って洗面器に湛えても良いし、道端に据えられた水盤や噴水でも良い。アクセスできる場所があれば、そこにデバイスを接続することで、個人IDに保存された設定が呼び起こされる。外部記憶として使えるだけでなく、情報端末にもなる。あるいは液相コンピュータを飲用水にすれば、今度は体内の健康状態を記録しモニタリングすることもできる。
そうして水の流れに沿って、人と情報は移動し、そこに文化が生まれていく。古代文明が川沿いに生まれたように。水があれば人が集まる。至って単純な文明の在り方が、また再現された訳だ。
鏡の向こうから
〝かきかたのせんせい〟として働くのは、毎週木曜日の午後3時から。その時間になれば、僕はカメラの前に立って、最適化された学習カリキュラムの通りに教えるだけ。
場所はどこでも良い。生徒のプロフィールは仮想現実内のもので、僕は彼らのアバターに向かって声を向ける。手触りの感覚も無く、人形を相手にした授業のように思ったこともある。それでもリアルタイムで反応してくれる子もいれば、後から個人的に説明を求める子もいる。その辺の機微については、昔の教師も大して変わらない、と教師業の先輩――祖父だけどね――からありがたいアドバイスを貰ったことがある。
時間になった。僕はファーストフード店の一角に陣取って、近くの水盤にヘッドセットデバイスを繋いで授業に臨む。拡張ホロが仮想現実を描き出し、水盤の上で僕と他数名のアバターを映しだした。
最初の生徒は三人だった。僕のような新米からしたら十分過ぎる。
一人は留学生らしく、日本の漢字に興味があったようだ。あとは女子高生が一人と、男子小学生が一人。個々人の習熟度は違うだろうが、教育プランナーの方でマッチングしている時点で問題は無いだろう。
「最初に、僕は漢字が得意なのでみんなに漢字の書き方を教えようと思います」
マイクで集音された僕の言葉が、リアルタイムで水盤の向こうの三人に伝わる。あるいは全員、授業を流しているだけで後から反応されるのかもしれないが。
「先生」
一人から発言があった。女子高生の子だ。リアルタイムに接してくれているのが嬉しかった。
「今どき、文字を手で書くのに意味があるんですか?」
それは当然の質問だと思った。僕も普段から手書きで何かを伝えることは少ない。ペンで文字を書いたとしても、プレディクティブ機能を使えば、液相コンピュータを溶かしたインクが前後の文脈を予測して自動的に文章を作ってくれる。そこにあるのは、形状記憶されたフォントだけ。
だからこそ、と説得することに決めていた。
「不立文字の精神だよ」
僕の言葉に三人の生徒から飛んでくる疑問符。
「単なる文字や言葉だけじゃ伝えられない、体験しなければ解らないことがあるという教えさ。つまり液相コンピュータや自動筆記、最適化されたサジェストに任せて受け取るだけじゃダメっていうこと。自分で書くことは、自分で選び取ることに繋がるはずだよ」
祖父からの受け売りだったが、その説明に生徒達は納得してくれたようだった。特にロシア人の生徒は感じ入ってくれたようで。
「でも、文字を勉強するんでしょう?」
ただ一人、女子高生からの全うなツッコミに、僕はどう答えるか悩んでしまった。