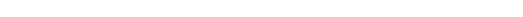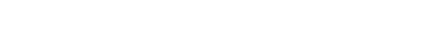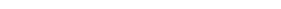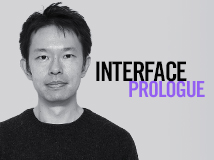倉田タカシ×INTERFACE
プロローグ
紙のオフィス:倉田タカシ
December 8, 2015
SF作家・倉田タカシさんが想像する、2036年の「インターフェイス」を全7回(短編小説4本+対談記事3本)にわたって紹介。短編小説のプロローグとなる本記事。新しい紙<パペル・ノヴァ>を円筒状に組み立てた『紙のオフィス』に閉じ込められた3人の男女。脱出を試みる彼らに去来する想いとは……。
大晦日、'36年
「店が終わっちゃうかな」
佐々波若南がつぶやくと、
「コンビニで酒買って、道で飲もうよ」
吉田ロニがいつものニヤニヤ顔で提案し、佐々波は苦笑する。
「そういう飲み方、もう10年以上してないわ……。まあ、今日もやんないですけどね、寒いし」
2036年の大晦日、夜の10時。外気温は3度。
比べれば、〈紙のオフィス〉の中は暖かかった。出られないことを気にせずにいられるなら、十分に快適だ。
横倒しにした円筒形の、特殊な紙で作られたこの大きな空間に、3人は閉じ込められている。
戸見計(とみ・けい)、男性、28歳のエンジニア。
佐々波若南(ささなみ・わかな)、32歳、衆議院議員で2児の母。
そして、ズィンガラマドゥニ星人の吉田ロニ(よしだ・ろに)。あご髭、痩せ型、40代。
「吉田さん、自分の星に連絡できないんですか」
「星、無いからね。吹っ飛んじゃったから」
「こないだは、まだあるって言ってましたけど」
「おれたちの心のなかにあるよ」
張りのある佐々波の声に、緊張感のない吉田の喋り。
やりとりを聞き流し、2人をここへ招いた当人である戸見は、手の中の紙をにらんでいる。
A4サイズのその紙にはカラーの印刷があり、遠目にはタブレットPCのメニュー画面とよく似ている。アイコンが並び、時刻表示がある。数字は刻々と変化している、つまり、『アニメーションして』いる。
あたらしい紙
戸見は顔のまえに紙をかざし、「分割、A5」と声に出す。紙面には小さな確認ウィンドウが現れる。
ウィンドウのなかにある『OK』のボタンを指ではじき、紙の端を両手でつまんで軽く引く。
ぴりぴりと軽快な音をたて、A4の紙はきれいに2枚のA5になった。紙のシステムが、分割線にあたる細い一直線の部分でだけ糊材の性質を変え、繊維の結合を弱めたのだ。
2枚に分かれた紙は、どちらも、もとの1枚に表示されていたメニュー画面を70%ほどに縮小して表示している。
この〈紙〉をつくる繊維のひとつひとつが、コウゾやミツマタのそれと同じ細さでありながら、大量生産の小さな電子機器でもある。それらが発光し、発色し、紙面をディスプレイにする。
最先端のナノファクチャリング、そしてラピッドプロダクション――『パペル・ノヴァ』がブランド名だ。
戸見の勤める会社がオフィス用の出力機器を開発し、シェアをほぼ独占している。
3人を閉じ込めている〈紙のオフィス〉も、〈パペル・ノヴァ〉で作られている。強度の高い外装も、壁の全面がディスプレイになっている内装も、すべて汎用のオフィス出力機からとり出され、組み上げられている。年明けに一般公開される、プレゼンテーション用の空間だ。
円筒の一方の端に設けられたドアから3人は入った。そのあとドアは開かなくなった。メニュー操作には反応がない。壁はとても硬い。――そして、電波は遮断されている。
「どう、なんとかなりそう?」
たずねる佐々波に、戸見はいま2つに分けた紙の片方を渡す。
仕掛けを披露する誇らしさが戸見の顔にでてしまったのだろう、佐々波はちょっとからかい顔で、吉田はやはりニヤニヤ顔で、紙を受けとる。
「これ、折ってください。折りかたをいまから教えます」。