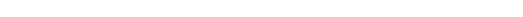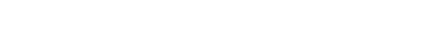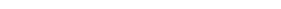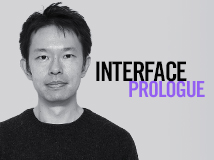倉田タカシ×INTERFACE
ストーリー1/3
ゆりかご:倉田タカシ
December 8, 2015
SF作家・倉田タカシさんが想像する、2036年の「インターフェイス」を全7回(短編小説4本+対談記事3本)にわたって紹介。短編小説の本編(1/3)となる本記事。『紙のオフィス』に閉じ込められた3人は、<パペル・ノヴァ>が“世代を仲立ちする”インターフェイスであることを認識する。その理由とは?
ひとを助ける
佐々波は、一人めの子をオフィスで生んだ。
クライアントの電話を受けているあいだに破水し、3時間後、ボランティアグループが運び込んだストレッチャーの上で、胸に新生児を抱き、同じクライアントと話していた。最終納品前日のことだ。
同じ職場にいた戸見は、自分の机で業務管理ソフトの画面を見つめながら産声を聞いた。
紙のついたてを通してフロアに響いた新生児の声は、戸見を目の前の業務から、それまでの人生から、はるか遠くへ吹き飛ばした。
「すごいイニシエーションだよね。佐々波さん、いいことしたじゃん」
吉田がいうと、佐々波はため息をつく。
「馬鹿だったなあって思ってますよ。夫がボランティアグループの緊急支援プログラムを申請してなかったら、ほんとにあぶなかった」
4年前のあの日、オフィスでの出産は、折り紙のちいさな飛行機によって幕を開けた。
室内に飛び込んだ紙飛行機は、ボランティアグループが来たこと、メンバーの医師がここで医療をおこなうのに法的な正当性があること、当人の許可を得ていること、などを宣言した。
戸見の目は紙飛行機に釘付けになる。それは〈パペル・ノヴァ〉で作られていた。
そして、紙飛行機のいう『当人』の名前を聞いてようやく、戸見と同僚たちは、佐々波が自分の席で上体をかがめ、机に額を押し付けていることに気づいたのだった。
グループの人々は、独自のやり方で〈パペル・ノヴァ〉を使いこなしていた。
紙の服を着たメンバーたちが佐々波を取り囲む。紙のついたてで簡単な医療ブースをつくる。使い捨ての服、顔を隠すマスク、佐々波の手首に留める心拍モニタ、どれもあの高機能素材の応用だった。
佐々波はそれからまもなく退職し、1年後、ボランティアグループの一員になった。一方、戸見は〈パペル・ノヴァ〉の開発企業に転職した。
さらに3年が過ぎたこの2036年、戸見はたくさんのニュース記事に佐々波の顔を見た。ボランティアグループは政党を立ち上げ、グループが支援してきた人々を支持層の基盤として、メンバーを何人も衆議院に送り込んだのだ。
「結成当初からグループの計画にあったのよ、国政への参加は」
いまの佐々波はそう説明する。
「水際で支援するだけじゃなくて、根本から変えていく必要があるって、わかってたんだよね」
これほどの規模と機動力をもつ組織だが、寄付だけで運営されているのだという。スタッフにもきちんと報酬が出ているらしい。
大規模かつ緻密なソーシャルデータ解析を駆使して、過重労働の現場で健康被害に直面する労働者を見つけだし、アプローチした。徹底的に個人に寄り添ったサポートで、心の支えになった。
――だから、基盤が強いのだ。
うつろいのインターフェイス
3人の手の中で、紙はしだいに複雑なオブジェに変わっていく。
対角線で山に折り、16等分した3つめで谷に折り、とがった先をかぶせ折り――
「ジオメトリ情報をそのままコードとして実行させるモードがあるんですよ」と戸見。
「折る位置や順序がプログラミング文になるって、おもしろいね。内容が長いほど、デカい紙が必要になるわけじゃん? それとも、圧縮する方法があんのかな」吉田のニヤニヤ顔が好奇心に満ちている。
「そんなに長い文は想定してないんで」
戸見は生真面目に答える。
佐々波の件があってから、戸見は、新しい働き方について考えるようになった。
全国にシェアを広げる途上にあった〈パペル・ノヴァ〉の企業にどうにか転職をはたし、今、ものを作る立場からオフィスのあり方を変えようとしている。
「不思議なのはさ、この技術って……」
紙を折る手を止め、佐々波が周囲の壁をみる。
「紙を、情報のコンテナじゃなくて、あくまでもインターフェイスとして扱ってるんだよね。戸見くんにとって、そこはどうなの?」
戸見も顔をあげ、視線をめぐらせた。
「僕、紙の本が好きじゃなかったんですよ」
〈紙の本〉というものに、戸見が初めて違和感をおぼえたのは、10歳のころだ。
「これ、死んでる! って思ったんですよ」
戸見の声に含まれた憤りに、吉田が吹き出す。
「何百枚も表示面を重ねて、それがひとつも反応しないって、すごく無駄じゃないですか。検索もできないし、コピーも面倒だし……」
「21世紀生まれの感覚なんだなあ」と吉田。
〈紙漉き〉を学校で体験したのも、同じころだった。
どろどろの繊維を掬って干すと、ぱりぱりとした紙に変わる。溶かせば、また元のどろどろになる。その流転と回帰のイメージが、戸見の心にいつまでも残った。
「――だから、〈パペル・ノヴァ〉のコンセプトは、僕にはすごくしっくりきました」
『紙のないオフィス』が目標とされていた時代があった。
その期待は、いっとき、タブレットPCなどの電子デバイスに寄せられていた。だが、これらは紙の役割をただ受け継ぐ道具ではない。むしろ紙にできなかったことを可能にするためのものであり、情報をもたらす〈窓〉としての使い方にこそ真価があった。
一方で、紙の利点はまだ求められていた。机のうえにたくさん広げて検討する、切り刻んで貼り合わせる、無造作にメモを書き込む――そんな使い方のできる現代的なツールへの要望が、〈パペル・ノヴァ〉の誕生をうながした。
電子デバイスを補完する形で〈パペル・ノヴァ〉は成長し、業界に深く根を張った。
折っても切り分けても表示データが保持される。インクペンでもスタイラスでも、あるいは指でも書き込むことができ、書いた内容も即座にデータ化される。タブレットPCと同様の端末として使うこともできる。用が済んだらすぐに回収・リサイクルされ、無駄な紙束が積みあがることもない。
永続性ではなく、うつろいを形にしたメディアとしての〈紙〉。
そして、開発にかかわるようになって戸見にもわかってきたのは、紙の形をとっていることの、別の意味での利点だ。
紙のほうが手に馴染んでいる年かさの世代と、電子デバイスを自在にあやつる若い世代が、この環境で一番よく折り合うことができる。ユーザー調査はそう語っていた。
『紙に出す』ことで、業務がスムーズに進む。いまはまだそういう時代なのだ。
「紙の形をしていること自体が、世代を仲立ちするインターフェイスなんだってことです」
「で、いま戸見くんはその先を考えてるのね」
この〈紙のオフィス〉は、〈パペル・ノヴァ〉がいかにオフィスを変えたかを集大成的にデモンストレーションするためのものだが、その先の展開を予告するものでもある。
オフィスのインフラから、都市のインフラへ――
それが、戸見の用意したコンセプトだった。
A5サイズの紙は、名刺ほどの大きさの、なにを模したともいえない、ややこしい折り紙になった。
これを人間が手にしていなければいけない。そして、3人が同時にアクションしなければいけない。
「悪用されたくないですから」と説明する戸見。
3人がおなじ形の折り紙を右手に持ち、同時に頭の上にかざす。
1・2・3――
5秒かぞえたら、手を下ろす。これを3回くりかえす。
センサが人の動作を察し、折り紙の形が読み解かれる。
ひと呼吸のあと、すべての壁がまっさらの緑に輝いた。〈紙のオフィス〉を再起動できたのだ。
……それから5分。
戸見は途方に暮れていた。
扉は、やはり開かない。
「おれたちがここで餓死しちゃう可能性、ちょっとある?」