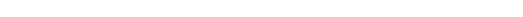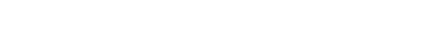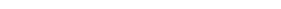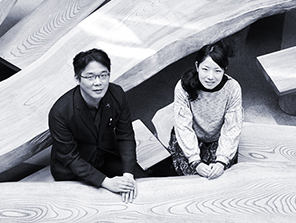柴田勝家×EDUCATION
プロローグ
「字心伝心」:柴田勝家
September 24, 2015
SF作家・柴田勝家さんが想像する、2036年の「教育」を全7回(短編小説4本+対談記事3本)にわたって紹介。短編小説の【プロローグ】となる本記事。街中の公園をはじめ、社会のあらゆる場所が公教育の場となった未来において、「進歩したもの」と「変わらなかったもの」とは……。
新しい教師像
僕がいわゆる〝教師〟になるって聞いて、一番に喜んだのは祖父だった。
若い頃に、熱血教師物なんていうジャンルのドラマを見て育ったのだそうだ。祖父にとって僕は、問題を抱えた生徒達を一所懸命に導く、誰からも慕われる立派な大人、ということらしい。
その期待は嬉しいけれど、果たして僕がそんなキャラクターを演じきれるかは、正直言って怪しい。友人の中には、あえて戯画化した教師像をトレースして演じている人もいるけれど、僕は至って普通、いつもの日常の中で必要とされたことを子供達に伝えるだけ。
僕は人生の全てを教えられる〝教師〟なんかじゃなくて、ただ少しだけ字の書き方を教えられる〝かきかたのせんせい〟なのだから。
ただの興味程度でも、人より得意なことがあるのは良いことだ。僕はたまたま人より漢字を扱うのが好きで、たまたま漢字書写検定と、それに付随する資格教諭検定を受けて、たまたま合格できただけだ。
自由な学業という方針の下で、義務教育時代の子供達は、自分の興味に合わせて校外授業を選択できる。小学生の頃から、一流企業の社長から経営学の薫陶を受ける子もいれば、ファッションデザイナーの手ほどきを受ける子もいる。漫画家やスポーツ選手の授業はいつだって人気科目だ。それだけじゃない。アナログゲームが得意な近所のお兄さん、歌の上手い綺麗なお姉さん、様々な地域の人が子供達の良き〝せんせい〟となっている。
それと変わって、いわゆる〝教師〟は、今では企業体の一部。学校法人の統廃合の先の先。それは、あらゆる学校施設を運営する、巨大な教育機能の中に組み込まれていった。理論的教育と教育工学を本業にする彼らは、単純な学習を外部――つまり僕らのような資格教諭――に任せて、より専門的なマネジメントと開発研究に時間を費やしている。
残念ながら漢字学習なんていう時代遅れなものは、彼ら〝教師〟の役目ではないらしい。じゃあ僕は何になった?
僕は数千、数万あるカリキュラムの一端を担う、数万、数億の教員の一人になっただけ。僕はなんでもない、本業は近所の水道局員のお兄さん。そんな人間が余技で教えるだけなのだ。
祖父の教え
僕が〝かきかたのせんせい〟になってから初めて、久しぶりに祖父のいる寺を訪ねた。
祖父は祖父で、昔は僧侶という人にものを教える立場だった訳だけれど、今では薄墨の僧衣をエプロンに変えて、三ツ星レストランのシェフから料理を学んでいる。
少子高齢化の先、学校教育と同じか、それ以上に重視された生涯教育の場。祖父は液相モニターの向こうのシェフの声に従って、茹で上がったパスタを取り上げる。
「見よう見まねだが、上手くなっただろう」
自慢の一品を仕上げてから、祖父はにっこりと笑ってみせた。
「不立文字さ」
祖父の優しい言葉は、迷っていた僕の心を少しだけ動かしてくれたようだ。僕は僕なりに、人にものを教えよう。立派な教師でなくても良い、人気のある職業でなくても良い、自分なりに、やってみよう。